メールマガジンを登録していただくと、セミナー・イベント開催のお知らせやブログの更新通知をお届けします
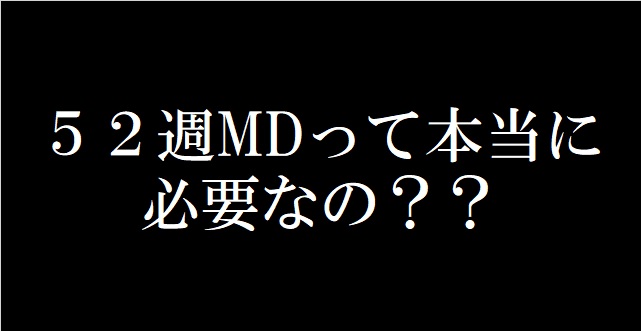
先日。繊研新聞さんで以下の記事を見つけました。
”52週MDの崩壊”
https://senken.co.jp/posts/mete-181218
常々。私は必要以上に、アパレル小売業において52週MDなど必要ないと訴えてきました。
(なぜ52週MDが必要ない?と感じる方は、下記の記事をご覧ください。)
”販売終了日?くらいはきめておこうよ ”
この業界の52週MDと言われるものは、ただの52週商品投入計画にすぎず、しかも、納期が少しでも遅れれば、その計画は水泡と帰し、現場は混乱に陥ります。
目的を見誤り、手段を目的のように考える。この業界の悪い慣習でしかありません。
しかし、このことを私のように否定すると、○○○○業界の方々から全面的に叩かれます(笑)
先ほど紹介した繊研新聞さんの記事では以下のように締めくくられています。
”服好きは、欲しいモノをネットで探すのが当たり前になった。天候不順が続くと、この時期はこういう服が売れるという前年踏襲のオリジナルも通用しない。
セレクトショップは縦売れするブランドや商品を消費者に先んじて見つけ、仕入れる力を改めて磨く必要がある。”
確かにその通りです。
しかし、セレクト業態は以前から、消費者に先んじてブランドを見つけようとする努力はしている筈ですし、仕入る力がなければそもそも”セレクト業態”など成り立つ筈もないものです。
また繊研さんの記事では”縦売れ”のことが触れられています。
MD・バイヤーは”縦売れ”する商品を仕入・開発することを目指しますが、そもそもが何故”縦売れ”するのかを、本質的な部分から考えることをしなければ、”縦売れ”などする筈もありません。
(商品を)顧客が欲しい!買いたい!という心理は何故生まれるのか?どこに付加価値を感じて購買に至るのか?そのことが”感覚”だけでなく、測定可能な指針を使用し論理的に掴むことができれば、その可能性は広がるかもしれません。
しかし現状のセレクト業態の弱点は、仕入形態など商品管理が複雑になるにも関わらず、管理が杜撰すぎるところです。もっと厳しい言葉で言うと、“ザル勘定”にみえるということです。
中には、MD等の管理で粗利を利用していないところさえあります。売れていた昔であれば、それでも儲かったのでしょうが、昨今の状況では在庫が膨れ上がるだけで、セール乱発による、ショップそのものがもつ付加価値が下がり続けています。
会計上でいう付加価値は”粗利益”になります。
顧客が付加価値を多く感じる商品は、セールする必要もなく売れます。その分。多くの粗利益が獲得できます。
また、元売価設定もMDにとって、大事な行為です。原価率ありきで顧客に対する付加価値を考えない売価設定は顧客にそっぽをむかれます。
今以上に”先んじるブランド”を探す。”感性”で勝負するという行為も大事なことではありますが、この情報社会では、おそらく他にすぐ追随されるだけでしょう。
であるならば、自分たちのブランド・ショップコンセプト。価格帯による顧客層。顧客に対する”付加価値”を商品面だけなく、測定することができる数字面からも相互に、そして結びつけて考え、顧客が欲しがる商品の開発の活かす。
このことが求められるのではないでしょうか。
MDの仕事における、商品面と数字面の仕事は車の両輪なのですから。。。
【(株)エムズ商品計画オフィシャルサイト】(株)エムズ商品計画代表取締役。大分県大分市出身。リテールMDアドバイザー。繊研新聞社より「数学嫌いでも算数ならできる筈〜算数で極めるMDへの道」出版。大手アパレルからライフスタイルブランド・スーパーマーケットなど、あらゆる分野のマーチャンダイジング改善に従事。唯一の趣味は古着収集。
小売ビジネスに関するMD(品揃え政策)アドバイス・サポートを
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。